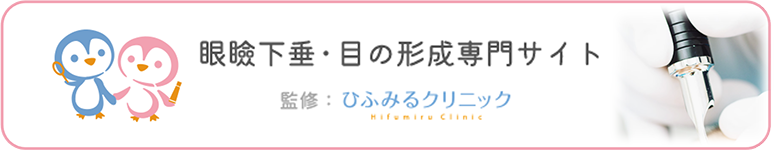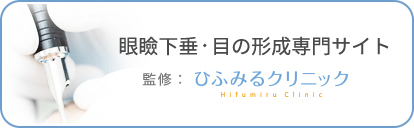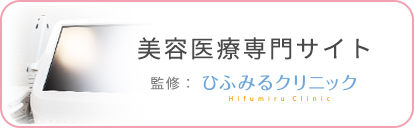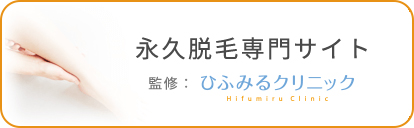眼瞼下垂の手術後にまぶたが二重になることがあると聞き、「自分は一重なのに二重に変わるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
確かに、眼瞼下垂の手術は一重まぶたが二重まぶたになりやすい特徴があります。しかし、一重のままでも眼瞼下垂の手術は可能であり、視野の改善や機能回復に問題が出ることはありません。
この記事ではどのような場合に二重になるのか、一重のままで眼瞼下垂を改善するのは本当に可能なのかなどについて紹介します。眼瞼下垂手術と一重まぶた・二重まぶたの関係について疑問のある方や、眼瞼下垂手術を受けても一重のままでいたい方は、ぜひ参考にしてください。
眼瞼下垂手術をしても一重のままでいられる?

もともと一重まぶたで、「眼瞼下垂手術をしても一重のままでいたい」と思う患者さんも多いでしょう。
ここでは、眼瞼下垂手術をしても一重のままでいられるのかどうか、手術の効果に違いはあるのかなどについて紹介します。
一重を希望する場合に伝えること
医師にはっきりとした希望を伝えておけば、切開ラインを奥二重に近い位置に調整するといった配慮が提案される場合もあります。
まず、眼瞼下垂の手術を受ける際に「一重まぶたのままでいたい」という希望がある場合は、術前カウンセリングで担当医にしっかり伝えましょう。
二重を提案される可能性もある
たとえ一重まぶたを希望していても、医師から「二重にしたほうがよい」と提案されることがあります。
手術の傷跡を二重のシワに隠し、仕上がりを違和感のないものにするためです。
一重のまま皮膚を切開すると、ライン上に傷跡が露出してしまう可能性があるため、術後の見た目を考慮してあえて二重まぶたを提案されるケースもあります。また、眼瞼下垂の手術では二重まぶたになることで視界改善や外見上の若返り効果も得やすいです。
そのため、医師側が機能面・美容面の両面からメリットを説明し、二重への移行をすすめてくる可能性も考慮しておきましょう。
一重のままでも視野改善や機能回復は可能
一重まぶたのままでも眼瞼下垂の機能改善は可能です。一重を維持したまま目の開きをよくする術式も存在します。
例えば、まぶたの縁ぎりぎりで皮膚を切開して挙筋を縫い縮める方法で眼瞼下垂を治療すれば、筋肉の機能を高めつつ、皮膚の厚みも取り除かれるため、目が開きやすくなります。この術式では傷跡がまつ毛の生え際付近に隠れるため、術後に目立つ心配もほとんどありません。
このほかにも患者さんの「一重のままでいたい」という希望を考慮しながら、眼瞼下垂の症状を改善できる手術方法があるため、医師とよく相談してください。
美容整形と眼瞼下垂手術の違い
眼瞼下垂手術は医学的にまぶたの機能を回復させるための治療であり、審美目的の二重まぶた手術(いわゆる美容整形)とは目的が異なります。
保険適用の眼瞼下垂手術では結果として二重まぶたになるケースが多いものの、それはあくまで副次的な効果で、本来の目的は上がりづらくなったまぶたを正常に開くようにすることです。
一方、美容整形の二重術は、生まれつき二重ではないまぶたに二重のラインを作ることを目的とした施術で、審美目的のため保険は適用されません。
眼瞼下垂手術で二重になる可能性があるのはなぜ?

個人差や手術上の要因、術後の腫れや癒着による影響などによっては、手術後に二重まぶたになる可能性が高い患者さんもいます。
ここでは、眼瞼下垂手術で二重になる可能性やその原因について紹介します。
まぶたの構造と反応の個人差
人それぞれのまぶたの構造の違いは、手術後の仕上がりに影響することがあります。
一般的に二重まぶたの人は、まぶたを上げる筋肉(眼瞼挙筋)から伸びる枝が皮膚に付着しており、まぶたを開けた時に皮膚を引き上げることで折り目(ひだ)ができます。一方、一重まぶたの場合はこうした付着がなく、まぶたを開けても皮膚が固定されないため折り目が生じません。
このような構造上の違いから、同じ手術を受けてももともとのまぶたの性質によって二重になりやすい方となりにくい方がいます。あらゆる可能性については事前に医師が説明するため、納得した上で手術を受けてください。
手術後に意図せず二重になる原因とは
眼瞼下垂の手術で二重まぶたになる要因のひとつに、上まぶたをしっかり上げるために皮膚を切開するステップがあります。
まぶたを十分に持ち上げるためには、皮膚や筋膜を切開し、筋肉を短縮・固定し直すステップが必要です。その結果、切開部位には余分な皮膚のひだが残り、それが二重のラインとして現れます。
手術の目的である「まぶたを上げる」を達成するために必要な処置のひとつとして、二重のラインができる可能性があるといえるでしょう。
ダウンタイム中の腫れや癒着の影響
術後のダウンタイム中の腫れや、傷が治る過程で生じる癒着(組織がくっついてしまうこと)も二重になる原因です。
手術直後からしばらくのダウンタイム中は、まぶたの腫れによって一時的にまぶたのラインが変化します。特に術後数日~1週間ほどは瞼が大きく腫れるため、本来より幅広い二重に見えたり、一重の人でも腫れによって奥二重から二重まぶたのように見えたりすることがあります。
一方、癒着もまぶたのラインに影響します。傷が治る過程で皮膚と下の組織が強く癒着すると、意図しない位置に皮膚が引き込まれて二重のラインが固定されてしまう場合があります。
適切な処置を行えば改善できる可能性もあるため、術後の経過で気になる点があれば早めに医師に相談してください。
「二重になった」と思ったら
もし術後に「一重のはずが二重になってしまった」と感じても、まずは医師に相談し、腫れが引いて落ち着くまで十分な時間経過を待つことが重要です。
原因と経過によっては再手術が必要になる可能性もありますが、すぐに行うかどうかは医師の判断になります。
再手術の多くは癒着部分を剥がし、挙筋の固定をやり直す術式です。ただし、再手術は最初の手術よりも難易度が高いケースも多く、新たなリスクも伴います。そのため、医師と十分に話し合い、再手術の内容やリスクを理解した上で慎重に判断しましょう。
当院、医療法人まぶたラボ ひふみるクリニックでは形成外科の専門医が対応し、患者さんの疑問や悩みが解消するまで丁寧に説明した上で手術や再手術のご案内をしています。再手術の可能性が生じ、ご不安などがあれば、どんなに小さなことでもお伝えください。
眼瞼下垂の術式・手術法

眼瞼下垂を治療する手術にはいくつかの術式があり、症状の程度や患者さんの希望、医師の判断などで選択されます。
ここでは、主な手術法について紹介します。
挙筋前転法
挙筋前転法は、伸びてゆるんでしまった上眼瞼挙筋の腱膜(けんまく)を短縮し、瞼板(けんばん)に縫い付け直すことでまぶたを持ち上げる術式です。
眼瞼下垂の手術の中では一般的に行われる方法で、筋肉の機能がまだある程度残っている、中等度までの眼瞼下垂に適していることが多いです。皮膚を切開し、腱膜をしっかり固定するため効果は長期間持続しやすく、重度の下垂でも改善が可能です。
切開を伴う手術のため、術後は切開部位が二重まぶたの線になりますが、必要に応じてラインを狭め、一重まぶたのままでいたいという患者さんの希望に合わせやすい特徴があります。
挙筋短縮法
挙筋短縮法は、上眼瞼挙筋の一部を短縮し、筋力を強化することにより眼瞼下垂を改善する術式です。
主に挙筋の働きが部分的に残っている症例に適用されることが多いです。皮膚を切開して行う場合、まぶたの開き具合を確認しながら調整できるため、効果が安定しやすい特徴があります。一方で、切開を伴わず糸で筋肉を縛る埋没法(いわゆる「切らない手術」)が挙筋短縮法に似ていると言われることもあります。
しかし、そもそも埋没法は美容整形手術の部類に入り、眼瞼下垂の根本的な治療ではありません。美容目的としては優れた術式ですが、眼瞼下垂の治療には向いていないことも確かで、再発するリスクが高いといえます。
再発すると再手術が必要になったり、症状によっては異なる術式の手術が必要になったりするケースもあります。当院では再発リスクを可能な限り軽減するため、眼瞼下垂の根本的な治療として切開を伴う手術をおすすめしています。
筋膜移植法(前頭筋吊り上げ術)
筋膜移植法(前頭筋吊り上げ術)は、挙筋の働きがほとんどなくなってしまった重度の眼瞼下垂に対して行われる術式です。
上まぶたを持ち上げる筋肉だけでは目を開けられない場合に、おでこの筋肉とまぶたを線維で繋いで引き上げる方法になります。
具体的には、大腿部から採取した筋膜や人工の繊維(ゴアテックスなど)を使用し、瞼板と前頭筋を連結させます。まぶたの皮膚や筋肉を切開して筋膜を通すため、基本的には切開した部分から二重まぶたになりますが、ラインを奥二重程度に設定し、一重まぶたに近付けることも可能です。
上眼瞼切開法(皮膚切除)
上眼瞼切開法(皮膚切除)は、上まぶたの余分な皮膚を取り除いて視野を改善する方法です。
挙筋の機能低下というより、皮膚のたるみ(眼瞼皮膚弛緩症)によってまぶたが下がっている場合に選択されることが多く、眼瞼下垂の手術と合わせて行われるケースもあります。
眉毛の下縁に沿って皮膚を切除する方法(眉下切開法)もあり、その場合は手術の傷跡が目立たないというメリットもあるため、美容的な悩みがある方にも向いています。
一重のまま目を大きくしたい場合は眉下切開が向いていることも
「できれば一重のままで目をパッチリさせたい」という場合には、眉下切開によるアプローチが適していることもあります。
眉下切開は眉毛直下を切開して上まぶたの皮膚を取り除く手術で、まぶたの構造には手を加えず、瞼の形を変えずに目を大きく見せやすいためです。ただし、眉下切開はあくまで皮膚のたるみを取る手術であり、眼瞼下垂の原因である挙筋の筋力低下そのものを改善する効果はありません。
保険は適用される?
眼瞼下垂と診断され、一定の基準を満たす場合には健康保険が適用されます。
例えば、以下のような基準が代表的です。
- 上まぶたが瞳孔にかかって視野が狭まる度合いが強い
- 日常生活への支障
- 眼瞼下垂にまつわる頭痛・肩こりの症状 など
このような医学的な判定基準に基づき、保険適用かどうかが判断されます。該当すれば保険診療として比較的安価に手術を受けることが可能です。
一方で、症状が軽度で日常生活に大きな支障がない場合や、「ぱっちり二重にしたい」といった美容目的の場合は保険適用外です。
眼瞼下垂の手術後の経過で気をつけたいこと

眼瞼下垂手術後は、二重に見えたり再手術の可能性などが気になる方もいます。
ここでは、眼瞼下垂手術後の経過で気をつけたいことについて紹介します。
手術直後の腫れと二重に見える関係
術後数日間は腫れが強く、その影響で一重まぶたが二重まぶたになったかのように見えることがあります。
このような腫れは通常術後2~3日から5日ほどがピークで、一般的には1週間前後で落ち着きます。二重まぶたになったように見えても焦らず、しばらく様子を見ましょう。
傷跡や癒着のリスクと対処法
眼瞼下垂手術の傷跡は時間とともに薄れていくものですが、個人差もあり、ごく稀に傷跡が肥厚したり癒着が強く残ったりするケースもあります。
傷の治癒過程で生じた癒着が原因で、二重ラインができてしまったり、傷跡が盛り上がって硬く残ったりする可能性もあるため、異変を感じたら早めに医師へ相談して改善案を求めましょう。
再手術が必要になるケースとは
眼瞼下垂の手術は、場合によっては再手術が必要になることもあります。
再手術になる理由としては以下のようなものが挙げられます。
- まぶたの開きが不十分だった
- 左右差が気になる仕上がりになった
- まぶたを上げすぎてしまった(過矯正) など
左右差やまぶたの上げすぎは、時間の経過によって落ち着くこともあるため、早急に再手術を行わずに様子見になることもあります。
いずれも術後の定期検診で医師が確認しますが、異変を感じている場合には必ず医師に伝え、より詳細な診察を求めましょう。
まとめ
眼瞼下垂の手術では切開を行う関係上、一般的には術後に二重まぶたになりますが、一重まぶたのままにしておくことも可能なケースが多いです。
一重まぶたのままで手術を終えても、まぶたを上げる機能回復や視野の改善に悪影響はありません。「一重まぶたのままがいい」という希望がある場合は、術前に担当医に伝えることでラインの調整や術式の検討がしやすくなるため、必ず伝えるようにしましょう。
医療法人まぶたラボ ひふみるクリニックでは、患者様お1人ひとりの症状やご希望に合わせた眼瞼下垂治療を行っています。
「一重のままで眼瞼下垂を改善したい」というご希望も、手術を担当する形成外科専門医が可能な限り対応いたします。「眼瞼下垂を改善したい、でも一重を変えたくない」などのお悩みがある方は、ぜひ当院でご相談ください。