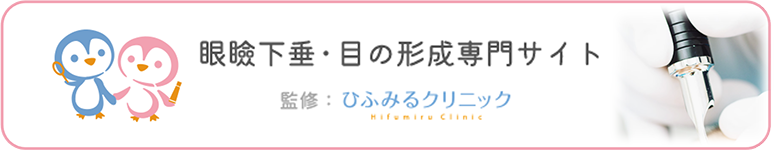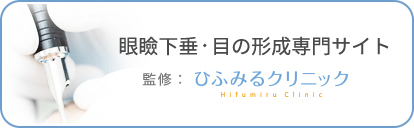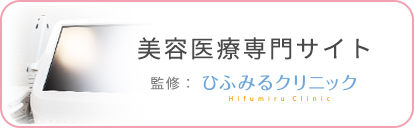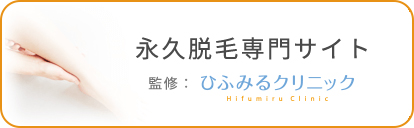眼瞼下垂(がんけんかすい)とは、上まぶたが下がって視野が狭くなる状態です。
近年、コンタクトレンズ(特にハードコンタクトレンズ)の長期使用が若い世代の眼瞼下垂の原因として注目されています。まぶたに違和感があり、コンタクトレンズを使っていることが原因かもしれないと思うことがあれば、眼瞼下垂とコンタクトレンズの関係や治療法などについて知っておくと役立つでしょう。
この記事では、眼瞼下垂の定義やコンタクトレンズとの関係、治療法、日常生活での注意点などについて紹介します。まぶたの違和感の原因や、眼瞼下垂とコンタクトレンズとの関係について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
眼瞼下垂とは?
まぶたや視界に違和感がある場合、さまざまな理由が考えられますが、そのひとつに眼瞼下垂(がんけんかすい)があります。
ここでは、眼瞼下垂の基本的な知識や症状などについて紹介します。
眼瞼下垂の定義と主な症状
眼瞼下垂とは、何らかの理由で上まぶたが下がり、目を開けにくくなる状態です。まぶたが垂れ下がって瞳孔を覆うため視界が狭くなり、物が見えにくくなります。
主な症状には以下のようなものがあります。
- まぶたが重い
- 上のほうが見づらい
- 額にシワを寄せないと物が見えない など
視野を確保しようと無意識に額の筋肉を使うため、頭痛や肩こり、眼精疲労などが起こることも多いです。見た目にも眠たそうな印象を与えてしまうため、自覚症状が少ない初期段階でも周囲から指摘されることがあります。
機械的眼瞼下垂とは
眼瞼下垂には先天性と後天性がありますが、後天性の中には「機械的眼瞼下垂」と呼ばれるタイプがあります。
これはまぶたへの物理的刺激(機械的刺激)によって、筋肉や腱膜が変化して生じる眼瞼下垂です。
主な要因には以下があります。
- まぶたや眼窩の腫瘍
- 交通事故による外傷
- アトピーや花粉症で目をこする行為
- コンタクトレンズ装用による刺激 など
特にハードコンタクトレンズの長期使用は、まばたきによる摩擦や物理的な力で挙筋腱膜(まぶたを持ち上げる筋肉の腱膜)がゆるみ、まぶたが下がる原因になります。
生活への影響と早期対応の重要性
眼瞼下垂になると視野狭窄が起こり、日常生活に支障をきたす恐れがあります。
例えば、以下のような影響が考えられます。
- 信号が見上げにくくなる
- 運転中に上方の視界が妨げられる
- 肩や首のこり
- 慢性的な頭痛 など
また、まぶたの下がりが急激に進行した場合、重症筋無力症や脳神経の疾患が隠れている可能性もあります。「最近まぶたが下がってきた」「夕方になると目を開けづらい」と感じた時点で、早めに専門医に相談しましょう。
コンタクトレンズと眼瞼下垂の関係

コンタクトレンズユーザーは眼瞼下垂に注意が必要です。
ここではハード、ソフトの各レンズと眼瞼下垂の関連性や、コンタクト装用習慣がまぶたに与える影響、専門家の見解について紹介します。
ハードコンタクトレンズと眼瞼下垂の関係性
ハードコンタクトレンズ(酸素透過性ハードレンズ)の長期使用は、レンズとの摩擦やまぶたへの刺激が蓄積され、眼瞼下垂のリスクになると考えられています。
摩擦や刺激は以下のような動作で起こりやすくなっています。
- 瞬きを繰り返す中で生じるハードコンタクトレンズとの摩擦
- ハードコンタクトレンズの着脱時にまぶたを引っ張る動作
いずれもハードコンタクトレンズを使う方にとっては日常的なことですが、眼瞼下垂の症状を起こしやすくする原因です。
ソフトコンタクトでは影響は少ないのか
ソフトコンタクトレンズは薄く柔らかい構造で、まぶたへの物理的負荷が比較的軽減されるため、ハードコンタクトレンズよりも眼瞼下垂のリスクが低いといわれています。
しかし、「ソフトコンタクトレンズなら絶対に安心」というわけではありません。ソフトコンタクトレンズでも、長期間の装用でまぶたを内側から圧迫し、摩擦や刺激を起こすことがあります。
扱い方によっては、ソフトコンタクトレンズでも眼瞼下垂のリスクがあることに注意しましょう。
レンズの装用習慣がまぶたに与える影響
コンタクトレンズの長期装用は、眼瞼下垂の発症や進行に影響を与えます。
主な影響として、以下が代表的です。
- まばたきをする時の摩擦
- コンタクトレンズ着脱時のまぶたの引っぱり
- まぶたを持ち上げる筋肉や腱膜への慢性的な負荷
- 炎症や刺激の反復が起こる可能性
まばたきによる摩擦や着脱時の負荷などは前述の通りです。
しかし、そのほかにも筋肉や腱膜への慢性的な負荷や、適切な衛生管理をしない場合に起こりやすい炎症の可能性などもあり、いずれも眼瞼下垂に影響します。
医師の見解や最近の傾向は?
近年、コンタクトレンズの長期使用による若年性の眼瞼下垂が増えており、医師の間でも注意喚起がなされています。
そのため、「眼瞼下垂予防のためにはハードコンタクトの使用中止、または控えることが望ましい」という意見も聞かれるようになりました。
特に、すでにまぶたの下がりが見られる人には、ハードコンタクトレンズからソフトコンタクトレンズへの変更や、眼鏡への切り替えをすすめる傾向も出ています。
眼鏡やそのほかの視力補正手段との比較

コンタクトレンズユーザーが眼瞼下垂を心配する場合、眼鏡への切り替えも選択肢のひとつです。
ここでは、眼鏡使用がまぶたに与える影響や、コンタクトから眼鏡に変えるメリット・デメリットなどについて紹介します。
眼鏡の使用が眼瞼下垂に与える影響
眼鏡は目に直接触れないため、まぶたへの物理的刺激がありません。
そのため、眼鏡の使用自体が眼瞼下垂の原因になることは基本的にないと考えられます。むしろ、コンタクトと眼鏡を併用して眼鏡をかける時間を増やすことで、まぶたへの負担を軽減しやすくなります。
例えば長時間コンタクトを装用する人でも、家では眼鏡に切り替える習慣をつければ、その分まぶたを休ませられるでしょう。
コンタクトから眼鏡へ変更するメリット・デメリット
コンタクトから眼鏡へ変更することにより、まぶたへの負担軽減をはじめとしたメリットが生まれます。
例えば、以下のような点はメリットになるでしょう。
- まぶたへの負担が大幅に減る
- ドライアイや結膜炎など、コンタクトで起こりやすいトラブルのリスク軽減
一方、デメリットについても見てみましょう。
- 見た目や装用感へのこだわりが反映されにくい
- スポーツの際に落下や破損の心配をする人もいる
どちらにするべきかは患者さん本人の選択になりますが、自身にとってのメリットやデメリットを考慮した上で決定しましょう。
まぶたの負担を軽減する工夫とは
眼鏡とコンタクトのいずれを使用する場合でも、まぶたに優しい工夫を取り入れることにより、眼瞼下垂のリスクを下げやすくなります。
例えば、以下のような方法を取り入れてみましょう。
- 眼鏡とコンタクトの併用
- レンズ装用の正しい手順を守る
- 部屋の湿度を保つ
- 整理整頓を心がける
- 乾燥を感じたら目薬を使う
眼鏡とコンタクトレンズの併用は、前述の通り、まぶたを休ませる時間を長く取れるようになります。
またレンズの着脱についても、正しい手順ならまぶたを無理に引っ張らなくても装用しやすいです。専用スポイトを使ったり、外す時は下まぶた側から外すなどの方法を意識しましょう。
部屋が乾燥したり散らかっていたりすると、乾燥感やホコリなどにより、目をこする回数が増えてしまうことがあります。湿度を適切に保ち、小まめな掃除を心がけることも、眼瞼下垂の予防や進行を抑えるために効果が期待できる方法です。
適切な補正手段の選び方
「眼鏡かコンタクトか」は一概にどちらがよいとはいえず、患者さん自身の目とまぶたの状態や好み、ニーズに応じて選ぶことになります。
もし眼瞼下垂が心配なら、一度形成外科や眼科で現状を診察してもらい、アドバイスを受けながら検討するとよいでしょう。
レーシックのような方法を選択した場合でも、すでにまぶたが下がっている場合にはやはり眼瞼下垂の治療が必要になることも多いです。そのような点も含めて考慮し、形成外科での相談も検討してください。
眼瞼下垂の治療法は?コンタクトはいつからOK?

実際に眼瞼下垂と診断された場合、どのような治療法があるのでしょうか。
ここでは、眼瞼下垂の手術や、手術後のコンタクト装用の注意点について紹介します。
まぶたを挙げる外科手術
眼瞼下垂の根本的な治療法は、外科手術によるまぶたの持ち上げです。
まぶたを持ち上げる筋肉(眼瞼挙筋)の機能低下や腱膜のゆるみが原因の場合、手術で筋肉や腱膜を正常な位置に再固定することで、まぶたがしっかり開きやすくなります。
手術の種類は複数ありますが、以下に代表的な手術法をまとめました。
| 手術法 | 内容 |
|---|---|
| 挙筋前転法 | 挙筋腱膜をまぶたに縫合し直す |
| 挙筋短縮法 | 眼瞼挙筋の切除・固定 |
| 上眼瞼切開法(皮膚切除) | 上まぶたの皮膚を切除・調整 |
| 筋膜移植法(前頭筋吊り上げ術) | 額の筋肉(前頭筋)とまぶたをつなぐ |
| 眉下切開 | 眉毛の下を切開してたるみを取り除く |
上記が主な術式ですが、患者さんの状態により適切な方法を医師が選択します。
医療機関にもよりますが、手術時間は30~40分程度、局所麻酔で行い、術後は1週間前後で抜糸となります。
多くの場合、日帰り手術での対応が可能です。当院でも日帰り手術に対応しており、忙しい方でも眼瞼下垂治療に取り組みやすい環境を整えています。
手術後のコンタクト装用はいつからできる?
医師の判断や手術後の回復にもよりますが、術後1か月間はコンタクトレンズの装用を控えましょう。
装用を控える理由には以下のようなものが挙げられます。
- 術後の傷口の安静と炎症防止
- 再手術防止と術後結果の安定化
早期にコンタクトを再開すると、治りかけた傷が開いたり、炎症がぶり返したりして、傷跡が厚く残ってしまうリスクがあります。また、着脱時の刺激で縫合した腱膜が外れてしまい、再手術の可能性もあるため、安定するまで装用は控えましょう。
医師によっては眼瞼下垂の再発や進行を抑えるため、手術後にコンタクトレンズの装用から眼鏡の使用をすすめることもあります。
眼瞼下垂と付き合うための日常生活の注意点

眼瞼下垂の症状がある方や手術後の方は、進行や再発を防ぐために、日常生活でいくつかの習慣を取り入れたほうがよいでしょう。
ここでは、眼瞼下垂と付き合うためにできる日常生活の工夫について紹介します。
まぶたへの刺激を減らす生活習慣
眼瞼下垂の予防や進行防止には、まぶたに過剰な刺激を与えないようにすることが大切です。
目が疲れたりかゆみを感じたりしても強くこすらず、花粉症やアレルギーの人は適切な点眼薬で対策をしてください。また、パソコンやスマートフォンの長時間使用は目やまぶたに負担がかかるため、適度に休憩を取りましょう。
メイクや洗顔時の注意点
強い摩擦や負荷はまぶたの皮膚や筋肉に負担をかけるため、アイメイクなどにも注意が必要です。
アイメイクを落とす際はゴシゴシと強く擦らずに、専用リムーバーを使い、優しく拭き取りましょう。
アイプチやアイテープも長期間使用するとまぶたの筋肉が疲労し、眼瞼下垂を招く恐れがあります。日常的な使用は控え、使った場合にはまぶたを十分に休ませる時間を取りましょう。
眼瞼下垂が疑われた場合の受診タイミング
「もしかして眼瞼下垂かも?」と感じたら早めに医療機関を受診してください。
特に、以下のような異変に気付いたら早めの受診をおすすめします。
- 片側、または両方のまぶたが下がる
- 二重幅や黒目の大きさに左右差がある
- 見えづらさや肩こり、額の疲れを強く感じる
- 他人から「目が小さくなった」と指摘される など
進行を見過ごすと生活の質が低下したり、さらに重症化したりするため、気になる症状があれば眼科や形成外科で診断を受けてください。
形成外科を受診するべき理由
眼瞼下垂が疑われる場合、まず眼科で診断を受け、必要があれば形成外科や専門クリニックを紹介されることが多いです。
手術は眼科と形成外科の両方で行われていますが、機能回復と見た目の自然さを両立したい場合は形成外科専門医が推奨されます。
当院でも形成外科の専門医が眼瞼下垂を診察・手術するため、患者さんの状態や希望に寄り添った治療が可能です。眼瞼下垂は保険診療で治療できる場合も多いため、費用面も含めてお気軽にご相談ください。
まとめ
眼瞼下垂は加齢だけでなく、ハードコンタクトレンズの長期使用など日常の習慣でも発症することがあります。
まぶたが下がると視野が狭くなり、頭痛や肩こりなど全身の不調につながることもあり、早期の対応が重要です。特にハードコンタクトユーザーは発症リスクが高いため、違和感があれば早めに使い方を見直しましょう。
医療法人まぶたラボ ひふみるクリニックでは、コンタクトレンズが原因の眼瞼下垂治療にも幅広く対応可能です。診察・手術の際には形成外科専門医が担当し、患者様1人ひとりに合わせた治療法や手術をご案内しています。
「コンタクトレンズが原因の眼瞼下垂かも」「まぶたの下がりが気になる」など、眼瞼下垂やまぶたに異変を感じたコンタクトレンズユーザーの方は、ぜひ一度当院へご相談ください。