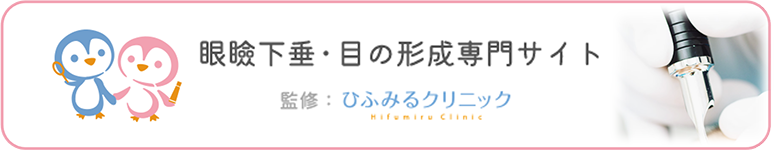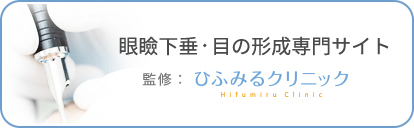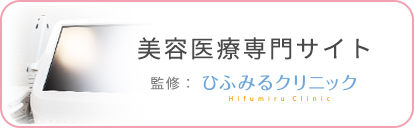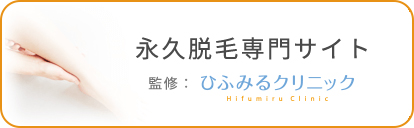眼瞼下垂(がんけんかすい)とは、上まぶたが正常な位置より下がり、目を開いたときにまぶたが黒目(瞳孔)の上まで十分に上がらない状態のことです。
この症状は単なる美容上の問題ではなく、視野の確保や日常生活にも影響しやすいため、異変に気付いたら早めの受診や治療が大切です。そのためには、眼瞼下垂の特徴や診断基準などを知っておくと、受診しやすくなるでしょう。
この記事では、眼瞼下垂の基礎知識や診断基準、セルフチェックの方法、受診するべき診療科や診断後に検討することなどについて紹介します。「眼瞼下垂かもしれない」「病院へ行くべき?」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。
眼瞼下垂とは?知っておきたい基礎知識

眼瞼下垂には先天性、後天性など原因による分類があり、放置すると見た目や日常生活に影響が出ることがあります。
ここでは、眼瞼下垂の基本や分類、放置した場合のリスクなどについて紹介します。
眼瞼下垂の定義と分類
眼瞼下垂は、正面を向いたときに上まぶたが黒目(瞳)を部分的に覆う、あるいは視界を遮る状態を指します。
主な分類は3つあり、それぞれ「先天性眼瞼下垂」「後天性眼瞼下垂」「偽眼瞼下垂」と呼ばれます。以下に各分類の特徴をまとめました。
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 先天性眼瞼下垂 |
・生まれつき筋肉や神経の異常が原因 ・片目に発症することが多い |
| 後天性眼瞼下垂 |
・多くが加齢やコンタクトレンズの長期使用が原因 ・別の疾患による発症の可能性もある ・成人後に発症することが多い |
| 偽眼瞼下垂 |
・一般的に一重瞼といわれる二重瞼ではない状態 ・美容外科的手術である埋没法などが選択される |
どの分類になるかは、専門医による検査と診断が必要です。「まぶたに違和感がある」と思ったら、早めに医療機関を受診しましょう。
見た目の問題だけではない日常生活への影響
眼瞼下垂は視野が狭くなり、上方が見えにくくなります。「まぶたが重く額が疲れる」「夕方に症状が強くなる」なども特徴です。
また、視界確保のために無意識に額の筋肉を使ったり、顎を上げたりすることが多くなり、その影響でシワや慢性的な頭痛、肩こりなどの原因になります。
放置することで起こり得るリスク
眼瞼下垂は自然に治ることはなく、放置すると進行する症状です。
例えば、先天性眼瞼の場合、視界が確保されないまま成長すると弱視になるリスクが上がります。加齢性の場合、視界不良や頭痛・肩こりが悪化しやすく、日常生活に影響が出たり、外見の変化による自信喪失や対人関係の問題が生じやすくなったりする恐れもあるでしょう。
中には「まだそれほど垂れていないから」と思い、受診を先延ばしにする方もいるかもしれません。しかし、眼瞼下垂は重症筋無力症のような病気に関わっている可能性もある症状です。受診が遅れれば全身疾患の発見が遅れるリスクもあるため、積極的な受診をおすすめします。
眼瞼下垂はどこで診断・治療する?何科を受診すべき?

受診をおすすめするといわれても、「どの診療科なのか分からない」「眼科と外科どちらがいいのか」と迷う方もいるでしょう。
ここでは、眼瞼下垂で受診・治療できる診療科について紹介します。
眼科
眼科は目の疾患や視力・視野の異常を専門とする診療科で、眼瞼下垂についても視機能の改善を目的に診断・治療を行います。
視界不良などの機能面の症状があり、病気の有無や治療の必要性を確かめたい方は、まず眼科を受診するのもひとつの選択肢です。眼科では眼瞼下垂だけではなく、ほかの目の病気や全身疾患との鑑別もより詳しく行います。
手術をする場合も保険適用になり、医療費を抑えながら、視野の確保を重視した治療が受けられる点が特徴です。
形成外科
形成外科は身体の表面や先天異常、外傷などを修復する専門科で、眼瞼下垂の診断・治療にも保険適用で対応しています。
特に、まぶたの外科的な修復が必要な場合や、機能回復と美容面の両立を希望する場合に適した診療科です。形成外科医は皮膚や組織の手術に精通し、傷跡の処置や仕上がりの美しさも考慮して手術を行います。
当院・医療法人まぶたラボ ひふみるクリニックでも、形成外科専門医が手術を行い、機能改善はもちろん、仕上がりに関しても可能な限り患者さんの希望に近付けています。
まずは眼科で診断を受け、形成外科での治療を検討するのもよい方法です。迷った場合には医師と相談して、適切な治療方針を選びましょう。
美容外科
美容外科での眼瞼下垂治療は、主に審美面の向上を目的としています。
「まぶたが少し下がって気になるのでパッチリさせたい」「二重の幅を理想的にしたい」など、見た目のデザインにこだわりがある場合に適しています。
ただし審美目的の場合は保険適用外になるため、全額自己負担になる点には注意が必要です。
眼瞼下垂の診断基準

眼瞼下垂の診断では、まぶたの位置や視野障害の程度など客観的な指標が重視されます。
MRD-1(黒目の中心から上まぶたの縁までの距離)が2.0mm以下の場合、眼瞼下垂と診断されることが多いです。さらに診断の際には、額の筋肉を使わずに自然な状態でどれだけ目を開けられるかも確認します。
このような検査に加え、以下のような症状が出ている場合は治療の必要性が高い可能性があります。
- 視野が狭くなった
- 慢性的に頭痛や肩こりを感じる
- その他、日常生活で眼瞼下垂が原因だと思われる支障がある
このような基準を満たし、医師が機能改善が必要と認めた場合は保険適用で手術が可能です。
眼瞼下垂の診断方法と検査の流れ

眼瞼下垂が疑われる場合、医療機関ではどのように検査や診断が進められるのでしょうか。
ここでは、問診で聞かれるポイントや、医師が行う測定(MRD値や筋機能検査)などについて紹介します。
問診で確認される主なポイント
最初に行われる問診は、眼瞼下垂の原因や程度の推測で重要なステップです。状態だけではなく、発症に関係すると思われる生活習慣や既往歴も確認されます。
以下のような質問が代表的です。
- 発症時期や経過について
- いつから発症したか
- どのように下がったか
- ハードコンタクトレンズの長期使用はあるか
- まぶたをこする癖はあるか
- 過去の眼科手術歴はあるか など
また、糖尿病、甲状腺疾患、重症筋無力症などの全身疾患や家族歴の有無も診断の精度を高める情報になるため、心当たりがあれば医師に伝えてください。
MRDや挙筋機能検査の内容
問診後、まぶたの状態を客観的に評価する検査が行われます。筋力と見た目の双方からチェックを行うための複数の検査です。
黒目の中心から上まぶた縁までの距離を表す「MRD-1」は、ミリメートル単位で測定され、基準値以下なら眼瞼下垂と診断されます。さらに、瞼裂高(上まぶた縁から下まぶた縁までの高さ)も確認し、左右差や開き具合を評価することも重要です。
また、「挙筋機能検査」では、額の筋肉を使わないように眉を押さえた状態で目を最大に開け、下を向いて目を閉じたときのまぶたの位置差(通常12~15mm)を測定します。値が小さい場合は筋力低下型、正常範囲なら腱膜性を考慮することが多いです。
このほか、上まぶたを一時的に持ち上げて皮膚のたるみと筋力の影響を区別する「プジーテスト」や、両方のまぶたの動きなどを確認する検査も行われます。
自覚症状を整理しておくと診断に役立つ
医師による検査だけでなく、患者さん自身が感じる自覚症状も診断の重要な手がかりです。
例えば、以下のようなことが分かる場合には、ぜひ医師へ伝えてください。
- まぶたが下がる状況や時間帯
- 眉や額への疲労感
- 信号が見えづらい、運転しづらいなど生活への影響
- 他人から指摘された内容 など
鏡で額の力を抜いて確認したり、他人に写真を撮ってもらうことで状態を把握しやすくなります。
診断に必要な具体的な検査手順
眼瞼下垂の検査では、問診、視診などのほか、視力検査や上方視野の欠損を調べる視野検査が行われます。
下垂の影響で視力低下や視野障害があれば、手術適応や保険適用判断の重要な情報になります。さらにドライアイや角膜障害の有無、眼球運動や神経学的なチェックも必要です。
こうした総合的な検査結果と自覚症状を踏まえて診断が下され、最後に医師から診断名や治療方針、保険適用可否などの説明を行います。
自分でできる眼瞼下垂のセルフチェック方法

医療機関を受診する前に、自分で簡易的に確認する方法で確認するのもおすすめです。
ここでは、眼瞼下垂のセルフチェック方法について紹介します。
鏡を使った具体的なチェック手順
自宅でできる眼瞼下垂のセルフチェックには、鏡を使った方法があります。
以下の手順でチェックしてみましょう。
- 鏡の前に立つ
- 上まぶたが黒目にかかっていないか確認する
- まぶたの皮膚が上まつげにかかっていないか
- 眉と額の動きに力が入っていないか
- 顎の位置が上がっていないか
この一連のチェックを行い、違和感がある場合には、眼瞼下垂の可能性を考慮したほうがよいでしょう。
次項の「チェック時に注目するべき3つのポイント」で詳しく解説します。
チェック時に注目するべき3つのポイント
セルフチェックを行う際には、以下の3つのポイントに特に注目してください。鏡で見るほか、写真を撮って確認してみるのもよい方法です。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| まぶたの位置 |
・上まぶたが黒目にどの程度被さっているか ・左右差が大きいかどうか |
| 皮膚のかぶり |
・まぶたの余分な皮膚が垂れて、まつ毛の生え際にかかっているか ・瞼が腫れぼったく、二重を作ってもすぐ戻らないか |
| 額・眉の動き |
・額にシワが常に刻まれていないか ・写真で眉毛が上がっているか |
片目ずつ交互にウインクしてみると、左右差や開けにくさにも気づきやすいです。
セルフチェックで注意するべき限界と誤差
セルフチェックはあくまで目安のため、正確な判断には限界があります。「当てはまるけど放っておいていいのかな?」「すぐ病院へ行くべき?」と判断に迷うこともあるでしょう。
しかし、眼瞼下垂は放置して改善することはなく、放置すれば進行するため、少しでも違和感があればぜひ受診してください。逆に、「気のせいだった」「単なる誤差だった」と判明すれば安心できる方も多いでしょう。
セルフチェックはあくまで参考にして、「おかしいな」と思った場合には眼科や形成外科で正確な診断を受けましょう。
眼瞼下垂と診断された後に検討するべきこと

眼瞼下垂の診断が出た場合、次は具体的な対策や治療を考慮する段階です。
ここでは、診断後に検討するべきポイントや、日常生活で心がけたいことなどについて紹介します。
日常生活での注意点とセルフケア
眼瞼下垂の進行を抑えるためには、医療的な治療のほか、生活の中で自分ができる対策を取り入れてみましょう。
- 目をこする癖をやめる
- ハードコンタクトレンズの使用を見直す
- 額や首の負担を軽減
- 眼精疲労対策
- 十分な睡眠と栄養バランスのよい食事
特にハードコンタクトレンズは、まぶたへの刺激が大きく、眼瞼下垂の発症率を高めやすいです。ソフトコンタクトレンズや眼鏡にするなど、ハードコンタクトレンズ以外の方法による視力矯正も検討しましょう。
治療の選択肢とその適応条件
眼瞼下垂の治療は基本的に手術になります。緩んだ筋肉や腱膜はトレーニングや薬で元通りにはならないため、外科手術が必要です。
眼瞼下垂の手術法は複数ありますが、ここでは代表的な治療法と、それぞれが適応になる条件などの一例を以下に紹介します。
| 手術法 | 内容 | 適用条件(例) |
|---|---|---|
| 挙筋前転法 | 挙筋腱膜をまぶたに縫合し直す | ・加齢性や腱膜性の眼瞼下垂の人 |
| 挙筋短縮法 | 眼瞼挙筋の切除・固定 |
・先天性眼瞼下垂の人 ・挙筋前転法で効果が実感しにくかった人 |
| 上眼瞼切開法(皮膚切除) | 上まぶたの皮膚を切除・調整 | ・まぶたの皮膚たるみが原因の人 |
上記の手術法のほか、切らない治療法もありますが、根本的な治療のためには、切る治療法をおすすめします。
診断書が必要になるケースとは
眼瞼下垂と診断された後、診断書が必要になるケースがあります。
具体的には保険会社への提出です。保険会社に給付金を申請する際、診断書の提出を求められることがあります。ただし、保険会社によっては一定の条件を満たしていれば診断書の提出が不要になることもあり、先に確認しておくことをおすすめします。
診断書は医療機関によって書式や費用が異なり、受け取りまで日数がかかることもあるため、必要になりそうな場合には、早めに医師へ申し出ておきましょう。
専門医へ相談する際に整理しておきたい情報
眼瞼下垂の治療で専門医に相談する段階になったら、事前にいくつかの情報を整理・準備しておくと診察がスムーズに進みやすくなります。
以下の情報を分かる範囲でまとめておきましょう。
- 発症時期や症状の変わり方
- (あれば)他科受診歴
- (あれば)他院の検査結果や紹介状
- 希望や不安のリスト
- 理想の仕上がりについて
仕上がりについては、保険適用か自由診療かで対応できる範囲が変わってきます。こだわりのある方は、医師と相談の上、「保険適用でどこまで対応できるか」「自由診療で対応したほうがよいか」などを検討しましょう。
まとめ
眼瞼下垂は、上まぶたが下がって目が開けづらくなる状態で、視界の悪化だけでなく頭痛や肩こりなど全身の不調につながることもあります。また、身体や神経の重大な病気が影響している可能性もあるため、まぶたの異変に気付いたら早めに受診してください。
眼瞼下垂は眼科、形成外科、美容外科で対応可能ですが、保険適用か自由診療になるかは医師の判断が必要になります。セルフチェックも活用しながら、適切なタイミングで受診しましょう。
医療法人まぶたラボ ひふみるクリニックでは、形成外科の専門医による診察・手術が可能です。また、ご希望の方には同院で美容外科を選択していただくことも可能です。眼瞼下垂のお悩みの患者様や、仕上がりにこだわりをお持ちの患者様も、お気軽にご相談ください。