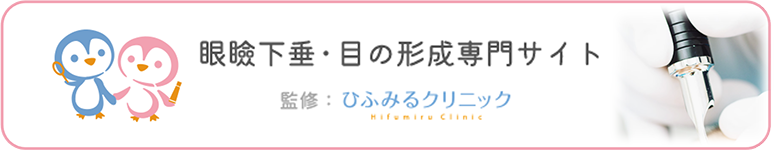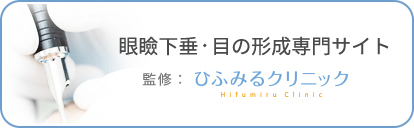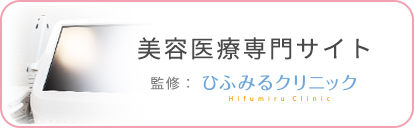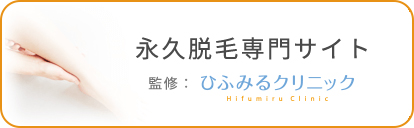まぶたが重く、目が開けにくいと感じる眼瞼下垂は、見た目の印象だけでなく、視界や日常生活にも影響を及ぼす症状です。
そんな眼瞼下垂に対して、「目薬で治せるのでは?」という声を耳にすることもありますが、実際の効果について気になる方も少なくありません。
この記事では、眼瞼下垂に対する点眼治療の実情や、市販の目薬とリスク、さらに有効とされる他の治療法について詳しく解説します。治療に不安がある方、まずは目薬で様子を見たいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
眼瞼下垂とは?

眼瞼下垂とは、上まぶたが垂れ下がり、黒目にかぶさり、視界を遮ってしまう状態を指します。
症状が進行すると、見た目の印象が変わるだけでなく、視野が狭くなることで日常生活に支障をきたすこともあります。
眼瞼下垂の症状と原因
眼瞼下垂の症状は、以下のようなものです。
- 上まぶたが垂れ下がり、視野が狭くなる
- まぶたが重く感じる
- 二重の幅が狭くなるなど見た目の変化
- まぶたを持ち上げようとして眉や額に力が入り、額にしわが寄る
- 顎を上げて物を見るようになる
- 周囲から「眠そう」と言われることがある
このような症状を引き起こす眼瞼下垂の原因は、主に以下の2種類に分けられます。
| 原因の種類 | 概要 |
|---|---|
| 先天性眼瞼下垂 | 生まれつきまぶたが垂れている状態。まぶたを持ち上げる筋肉の発達異常やそれを動かす神経の異常が原因とされる |
| 後天性眼瞼下垂 | 加齢や生活習慣によってまぶたを持ち上げる眼瞼挙筋の付け根にある腱膜がゆるみ、まぶたが垂れる |
このほかにも、まぶた自体や筋肉・神経に問題がないにも関わらず、他の病気や状態によりまぶたが下がっているように見える偽眼瞼下垂もあります。
後天性眼瞼下垂になりやすい生活習慣は、加齢・目をこする癖・ハードコンタクトレンズの長期使用・パソコンやスマートフォンの長期使用などです。
眼瞼下垂かどうかは、形成外科や眼科で医師によって診断されます。眼瞼下垂は放置していても改善することはなく、むしろ重症化すると日常生活に影響が及ぶため、気になる症状がある場合は早めの受診をおすすめします。
眼瞼下垂のセルフチェック
症状を見て、眼瞼下垂と疑われる場合、自宅で簡単に確認できるセルフチェック方法があります。
- リラックスした状態で目を軽く閉じ、顔を正面に向ける
- 左右の眉の上に指を軽く添えて、動かないように押さえる
- そのままの状態でゆっくり目を開ける
この時、スムーズに目が開けば、眼瞼下垂の可能性は少なくなります。
一方で、目を開けるのが難しかったり、額に力が入るようであれば、注意が必要です。無意識に額の筋肉を使ってまぶたを引き上げている状態である可能性が高いため、医療機関で診察を受けましょう。
眼瞼下垂に目薬は効く?

結論から言うと、目薬では眼瞼下垂の根本的な改善は期待できません。
一時的にまぶたが持ち上がるように感じる効果がある目薬もありますが、根本的な改善にはつながらず、むしろ症状を悪化させる可能性もあります。
眼瞼下垂は、まぶたを持ち上げる筋肉やそれを支える組織がゆるむことで起こります。目薬のような外的な刺激では、この構造的な問題を解決することはできません。
眼瞼下垂の点眼治療薬
眼瞼下垂を治す目薬とうたっている、交感神経に作用して一時的にまぶたを引き上げる目薬が存在します。
たとえば、塩酸テトラヒドロゾリンなどの血管収縮成分を含む目薬は、まぶたの筋肉に一時的な収縮を起こし、わずかにまぶたが上がることがあります。しかし、この効果は一時的なもので、治療とは呼べません。
しかも、こうした目薬は瞳孔を広げる作用もあるため、緑内障を持つ人にはリスクが高く、使えないことが多いです。
また、近年では、後天性眼瞼下垂に対応した新しい目薬の治験が行われており、日本の製薬会社が製造販売の承認申請をしています。しかし、現時点ではまだ販売には至っておらず、処方もできない状況です。
市販の目薬は眼瞼下垂に効く?
市販されている目薬の多くは、乾きや疲れ目、充血といった症状の緩和を目的としています。
しかし、眼瞼下垂への効果は期待できず、むしろ状態を悪化させる原因となる場合もあります。
角膜にダメージを与える可能性
市販の目薬には保存性を高めるための防腐剤が含まれていることがあり、過剰に使用すると角膜を傷つけるリスクがあります。
角膜のバリア機能が低下することで、目の表面の健康が損なわれ、結果的に眼瞼下垂の症状が進行することも考えられます。
涙の3層構造が崩れる
涙は、油層・水層・ムチン層の3層からなり、目の保護や潤滑に重要な役割を果たしています。
目薬を頻繁に使用すると、この涙のバランスが崩れ、目の乾燥や刺激感が増し、まぶたの筋肉や機能にも悪影響を及ぼす可能性があります。
緑内障用の目薬は特にリスクが高い
まつ毛が伸びる薬として販売されている目薬には、緑内障治療に使われるプロスタグランジン関連薬があります。
これらの薬剤は、眼球周囲の組織に変化をもたらす副作用があり、眼瞼下垂を引き起こすことがあります。こうした副作用は使用を中止すれば軽快することもありますが、進行すると外科的な治療が必要になるケースもあります。
眼瞼下垂の目薬以外の治療法

眼瞼下垂の治療には、症状の進行度や原因に応じてさまざまな方法があります。
目薬による対処は根本的な改善にはつながらないため、多くの場合、筋肉や皮膚へのアプローチが必要になります。軽症であれば、日常的なセルフケアで進行を遅らせることも可能ですが、症状が明らかな場合や視界に支障をきたすようであれば、外科的な治療が検討されます。
軽度の場合はトレーニングやマッサージ
まぶたの動きに関わる筋力の衰えが軽度な段階であれば、以下のような自宅ケアを取り入れることで改善が期待できます。
| マッサージや生活習慣 | 方法 |
|---|---|
| まぶたの筋力トレーニング | まぶたをぎゅっと閉じてから、ゆっくり大きく開くという動作を繰り返すことで、眼瞼挙筋を刺激し、筋肉の活性化を図る |
| 目の周りのマッサージ | 目の上や目頭・目尻周辺をやさしくなでるようにマッサージすることで血行が促進され、眼の周囲の筋肉がほぐれやすくなる |
| ピントトレーニング | 遠くのものと近くのものを交互に見る習慣をつけることで眼球周辺の筋肉が鍛えられ視界の安定にも役立つ |
| 姿勢の見直し | 長時間下を向いてスマートフォンを使用したり、無理な体勢で画面を見続ける習慣はまぶたに負担をかけるため、正しい姿勢を心がける |
こうした方法は、日常生活に取り入れやすく、軽度の症状に対しては一定の効果が見込めますが、根本的な改善にはつながりません。
信頼できる医療機関での経過観察を続けながら、相談しながら治療計画を立てることが大切です。
眼瞼下垂手術の種類
眼瞼下垂が中等度以上に進行している場合や、視界の確保が難しい状態であれば、手術による治療が必要になることがあります。
原因や症状に応じて、以下のような術式が選択されます。
挙筋前転法
まぶたを持ち上げる眼瞼挙筋の腱膜が、まぶたの軟骨(瞼板)から外れている場合に行う手術です。
ゆるんだ腱膜を再び瞼板に固定し直すことで、まぶたが本来の位置まで上がるようにします。比較的広く用いられる基本的な術式です。
挙筋短縮法
眼瞼挙筋そのものが大きく伸びている、または機能が大きく低下している場合に適している方法です。
筋肉を部分的に切除・短縮してから再接続することで、まぶたを引き上げる力を回復させます。重症の眼瞼下垂に対応することが多い手術法です。
上眼瞼切開法(皮膚切除)
まぶたのたるみによって視界が遮られている場合に適用されます。
余分な皮膚を取り除き、必要に応じて脂肪や筋肉のバランスを調整することで、自然な目元と視野の確保を両立させる方法です。身体への負担が比較的軽く、回復も早いのが特徴です。
筋膜移植法(前頭筋吊り上げ術)
まぶたを動かす筋肉がほとんど機能していない場合に行われる高度な手術です。
眉を上げる役割を持つ前頭筋とまぶたを連結し、代わりに眉の動きでまぶたを開けられるようにします。自分の大腿筋膜を採取して使用するのが一般的で、先天性や神経障害に由来する重度眼瞼下垂に用いられます。
眼瞼下垂の目薬についてのよくある疑問

眼瞼下垂と目薬の関係について、SNSなどでさまざまな情報を目にすることがあります。
中には目薬で眼瞼下垂といった内容も見かけますが、実際のところはどうなのかという疑問もあります。また、手術後に目薬が処方される理由についても気になっている方もいるようです。
ここでは、上記の2つの疑問について解説します。
SNSで目薬で治ったと聞いたのですが
SNSや口コミで、目薬で眼瞼下垂が改善したといった声を見ることがあります。
ただし、これは非常にまれなケースか、厳密には眼瞼下垂ではない別の症状だった可能性があります。
眼瞼下垂は、上まぶたを持ち上げる筋肉(眼瞼挙筋)や神経に原因があるため、基本的には目薬だけで治すことはできず、医療機関での診断・治療が必要な疾患です。市販の目薬や美容系の製品の中には、まぶたのハリ感や一時的な引き締め効果をうたうものもありますが、こうしたものは根本的な改善にはつながりません。
眼瞼下垂の手術後にも目薬が処方されました
眼瞼下垂の手術後に目薬が処方されるため、眼瞼下垂の治療に目薬が使われるという誤解につながっている可能性がありますが、この目薬はドライアイ治療の目薬です。眼瞼手術の手術後には、ドライアイの症状が出やすくなります。
これは、手術によってまぶたがしっかりと上がり、目の表面が空気に触れる範囲が広がるためです。さらに、術後しばらくはまぶたを完全に閉じにくくなることがあり、特に就寝中に眼が開いたままになりやすく、目の乾燥を引き起こす原因になります。
このため、ほとんどの医療機関では、手術後の乾燥対策として保湿用の目薬を処方しています。この目薬は、目の潤いを保ち、不快感をやわらげるのが主な目的です。
ドライアイの症状は、術後1~2か月ほどで自然と軽快することが多いですが、放置すると視力の低下や頭痛、角膜の傷など、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。
なお、市販の目薬には防腐剤や刺激の強い成分が含まれることもあるため、術後は医師の指示に従い、処方された目薬を使うようにしましょう。
まとめ
眼瞼下垂は、目薬だけで根本的に改善することは難しく、むしろ目薬の種類によっては角膜や涙のバランスに悪影響を及ぼす可能性もあります。
軽度のうちはセルフトレーニングなどで様子を見る場合もありますが、多くの場合、状態に応じた手術による治療が有効です。症状に合わせた適切な治療法を選ぶためにも、まずは形成外科や眼科の専門医に相談することをおすすめします。
『ひふみるクリニック』では、眼瞼下垂に関するご相談を随時受け付けております。患者さんの不安を解消し、納得のいく治療をするよう心がけておりますので、気になることがあればお気軽にお問合せください。