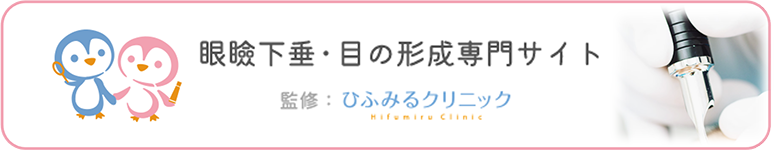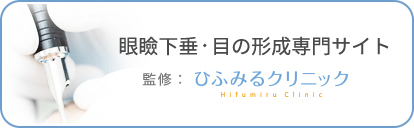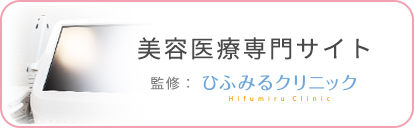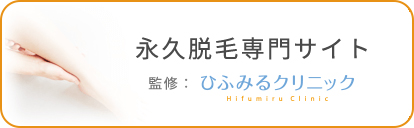「最近まぶたが重い」「目が開けにくくなってきた気がする」そんな違和感を覚えたら眼瞼下垂かもしれません。
眼瞼下垂とは、まぶたが下がってしまう状態を指し、放置すると視界が狭くなるだけでなく、見た目の印象や肩こり・頭痛の原因にもなる場合があります。
眼瞼下垂は日頃のトレーニングや生活習慣の見直しによって予防できるケースもあります。
この記事では、眼瞼下垂の症状や原因、セルフチェック法や予防に効果的なトレーニングなどをわかりやすく解説します。病院で行われる治療法も紹介しますので、目元に違和感のある方はぜひ参考にしてください。
眼瞼下垂とは

眼瞼下垂とは、上まぶたが正常な位置より下がってしまう状態を指します。まぶたが目にかぶさることで、視界が狭くなったり、目元の印象が変わってしまったりすることがあります。
この症状は大きく分けて、先天性と後天性の2種類があります。
| 先天性眼瞼下垂 | 生まれつきまぶたを引き上げる筋肉や神経の発育に異常があり、出生時からまぶたが下がっている状態 |
|---|---|
| 後天性眼瞼下垂 | 年齢を重ねるにつれてまぶたが徐々に垂れ下がってくるもので、主に加齢による筋肉や腱のゆるみが原因 |
特に後天性は中高年に多く見られ、「最近目が開けにくい」「年齢とともに目が小さく見える」と感じた場合、眼瞼下垂が進行している可能性があります。
症状・原因
眼瞼下垂の主な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- まぶたが重く感じる
- 視野が狭くなってきた気がする
- 額や眉に力を入れないと目が開かない
- 二重のラインが変わってきた
- まぶたのたるみで実年齢より老けて見られる
- ものを見る時に顎を上げる癖がついている
また、見た目の変化だけでなく、頭痛・肩こり・眼精疲労といった症状につながることも少なくありません。
後天性眼瞼下垂の場合の原因は、加齢だけでなく、コンタクトレンズの長期使用・目を強くこする癖・日常的なアイメイクやクレンジングによる刺激などがあります。これらの行動は、まぶたを引き上げる腱膜に負担をかけ、後天性眼瞼下垂のリスクを高めると考えられます。
眼瞼下垂のセルフチェック
眼瞼下垂の疑いがあるかどうか気になる場合は、以下のセルフチェックを試してみましょう。
- 顔を正面に向けたまま、目を軽く閉じる
- 両眉の上を指で軽く抑えた状態で、目をゆっくり開ける
- この状態で額に力が入る、まぶたがなかなか開かない場合は眼瞼下垂の可能性がある
この動作で眉の力を借りずに目を開けられない場合、日常的におでこの筋肉を使って目を開けている可能性があります。これは、まぶたを持ち上げる筋肉の機能が低下しているサインです。
セルフチェックで気になる結果になった場合は、眼科や形成外科などの専門医に相談することをおすすめします。
重度の場合は手術を検討
眼瞼下垂の進行が進み、視界への影響や生活の質に支障をきたしている場合は、手術による治療が選択肢となります。
最も一般的なのは、挙筋前転術という手術で、まぶたを引き上げる筋肉や腱膜のゆるみを修正し、自然なまぶたの位置に戻すものです。症状の原因や重症度によっては、他の術式が選ばれることもあります。
特に、視野障害や頭痛、慢性的な肩こりなどが生じている場合は、保険適用での手術が可能となるケースがあります。手術を検討する際は、眼瞼下垂の症例が豊富な医療機関で、症状や生活への影響を踏まえたうえで判断することが大切です。
眼瞼下垂のトレーニングは効果がある?

眼瞼下垂は、ストレッチやマッサージで治るものではありません。特にすでに症状が進行している場合は、自力での改善は難しいでしょう。
ただし、眼瞼下垂の予防という観点では、目元の筋肉を意識的に使うトレーニングが一定の効果を発揮する可能性があります。
眼瞼下垂自体の改善は難しい
一度下がってしまったまぶたを、ストレッチやマッサージだけで元に戻すことは非常に困難です。特に腱膜性の眼瞼下垂は、まぶたを持ち上げる筋肉の腱が緩んでいる状態であり、トレーニングやマッサージで元に戻すことは期待できません。
また、まぶた周辺を強く刺激するマッサージは、皮膚や筋肉などを痛めてしまい、かえってたるみやくぼみを悪化させてしまうリスクがあります。
セルフケアで一時的に症状を和らげる方法(テーピングなど)は存在しますが、根本的な解決にはつながりません。そのため、症状が明らかな場合には、医療機関での受診や治療を検討することが適切と言えるでしょう。
眼瞼下垂の予防にはトレーニングは有効
トレーニングは、眼瞼下垂の予防として有効です。
特に、加齢や習慣により目元の筋肉が衰えてくる前に意識的に鍛えておくことは、予防対策として有効です。眼瞼挙筋や眼輪筋といった目元の筋肉をトレーニングすることで、まぶたが下がりにくくなり、目元の印象を若々しく保つことができます。
特別な道具は必要なく、簡単な運動を継続的に行うことで日常的にケアができます。次の項目で、具体的なトレーニング方法を紹介するため、ぜひ参考にしてください。
眼瞼下垂を予防するためのトレーニング法

眼瞼下垂の予防に効果的とされる具体的なトレーニング方法を紹介します。
どれも短時間で実践できるため、仕事や家事の合間に行ってみてください。
眼瞼挙筋を鍛えるトレーニング
まぶたを持ち上げる筋肉である眼瞼挙筋をトレーニングすることで、まぶたが下がるのを予防します。
- 額の力を抜いて目を閉じる
- 手のひらで左右の眉毛が動かないように軽く固定する
- 両目を限界まで大きく開いて5秒キープする
- ゆっくり目を閉じてリラックスする
上記の4つの手順を1セットとして、1日数回実施することで眼瞼挙筋の衰えを防げます。
重要なのは、額の筋肉を使わず、まぶたの筋肉だけを動かす意識を持つことです。
ウインクやまばたきのトレーニング
目の周りの筋肉(眼輪筋)を刺激することで、血行改善やたるみ予防につながります。
ウインクやまばたきを意識して行うだけでトレーニングになりますので、ぜひ行ってみましょう。
ウインクトレーニング
ウインクトレーニングは以下の手順で行います。
- 右目でウインクを1回
- 左目でウインクを1回
これを左右交互に5回ずつ、1日に数セット行いましょう。
まばたきトレーニング
まばたきを以下のように意識して行うことで、目の周りの筋肉のトレーニングにつながります。
- 上を向いて両目でまばたきをする
- 同様に、右・左・下方向を向いてまばたきする
こちらもウインクトレーニングと同様に、上下左右それぞれ5回ずつ、1日数セットが目安です。
眼瞼下垂がトレーニングでも予防・改善できなかった場合

眼瞼下垂が進行してしまった場合、セルフケアやトレーニングでは十分な改善が見込めないことがあります。まぶたが視界を遮るほど下がってしまったり、目の開けづらさで日常生活に支障が出ている場合は、医療機関での診療と治療が必要です。
医師の判断により、保険適用でも治療や手術が可能になるケースもあります。
ここでは、治療に進む前に知っておきたい検査内容や治療法、保険適用の可否、自由診療との違いについて解説します。
病院での検査内容
眼瞼下垂が疑われるとき、医療機関では、視野や眼瞼の開き具合の検査を行います。
主な検査内容は次のようなものが一般的です。
- まぶたの垂れ下がりによる視野の狭まり具合を確認(視野検査)
- 瞳孔中央から上まぶたの縁までの距離を測定(MRDの測定)
- まぶたを持ち上げる筋肉の働きの程度を調べる(挙筋機能の評価)
必要に応じて、脳神経や筋疾患など他の疾患が隠れていないかを確認するために、MRIや血液検査を行う場合もあります。
保険適用での治療が可能なケース
眼瞼下垂は保険適用で治療できる場合と、自由診療になるケースがあります。
保険診療が適用されるのは、以下のような症状がある場合が一般的です。
- まぶたが下がって視界を遮っている
- 見えにくさにより日常生活に支障がある
- まぶたが下がっていることで頭痛や肩こりなどを引き起こしている
- 上まぶたの筋肉や腱膜が機能していない
見た目の改善を目的としたケースは保険適用の対象外となり、自由診療扱いとなります。
保険適用での手術
医師によって眼瞼下垂と診断され、保険適用の基準を満たした場合は手術が行われます。多くの場合、日帰り手術となり、局所麻酔や笑気麻酔などが使用されます。
代表的な術式は次のようなものがあります。
| 手術名 | 適応状況・原因 | 手術内容 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 挙筋前転法 | 挙筋腱膜が瞼から外れている場合 | 挙筋腱膜を瞼に縫合し直して垂れ下がりを改善 | 典型的な眼瞼下垂の手術方法 |
| 挙筋短縮法 | 重度の眼瞼下垂・筋肉の弛緩 | 弛緩した眼瞼挙筋の切除や短縮、固定によってまぶたを引き上げる | 挙筋の筋力がまだある重度下垂に対応 |
| 上眼瞼切開法 | 上瞼の皮膚の弛緩 | 上瞼の余剰皮膚を切除・調整して症状改善 | 術後の腫れが少なく、患者の負担も少ない |
| 筋膜移植法 | 眼瞼挙筋がほぼ機能していない状態 | 額の筋肉とまぶたを筋膜でつなぎ、前頭筋の力でまぶたを持ち上げる | 自身の大腿筋膜を使用することが多い |
| 眉下切開 | 眉下の皮膚のたるみ | 眉毛下を切開し、たるみを除去 | まぶたに手を加えず自然な印象 |
これらの手術の術後は数日間の腫れや内出血、2~3か月の赤みが続くことがあります。
保険適用での手術は視野改善が目的であるため、見た目の細かな調整には限界があります。
自由診療での手術
美容的な改善や見た目のこだわりが強い場合には、自由診療が選択されます。
例えば、以下のような希望がある場合は、自由診療の手術になる可能性があります。
- 二重の幅やラインを細かく指定したい
- 左右差や黒目の見え方までこだわりたい
- 軽度のたるみや見た目の若返りを重視したい
自由診療では、カウンセリングを重ねながら理想のまぶたを目指せる点がメリットで、患者さんの希望に沿った繊細な仕上がりが可能です。ただし、費用は全額自己負担となり、術後の修正が必要な場合も追加費用がかかる可能性があるため、事前に確認が必要です。
眼瞼下垂になりやすくなるNG行動

眼瞼下垂は一度発症してしまうと、トレーニングやマッサージでは根本的な改善が難しく、進行具合によっては手術が必要になることもあります。
だからこそ、日頃の行動で眼瞼挙筋に負担をかけないことが大切です。
ここでは、まぶたの筋肉や皮膚にダメージを与え、眼瞼下垂を引き起こす原因となりやすいNG行動を4つ紹介します。当てはまる習慣があれば、今日から少しずつ見直してみましょう。
ハードコンタクトの長時間使用
ハードコンタクトレンズは、装着時にまぶたの裏側にレンズが直接当たり、眼瞼挙筋腱膜への微細な刺激を繰り返します。また、装着した状態でまばたきを繰り返すことでも、まぶたを内側から圧迫して擦る刺激となります。
コンタクトレンズを外す際にも、まぶたを強く引っ張ると眼瞼挙筋に負担をかけるため、下まぶたを下げて外すのがおすすめです。
日常的にコンタクトを使っている方は、休日や在宅時はメガネで過ごすなど、まぶたを休ませる時間を作りましょう。
アイプチなどの目を引っ張る行動
二重まぶたを作るアイテムとして多くの方が使っているアイプチやアイテープですが、使用方法によっては眼瞼下垂を悪化させる要因になります。
特に、のりを落とす時に皮膚を強く引っ張ったり、繰り返し無理な力でまぶたを開かせたりすることで、眼瞼挙筋に過度なストレスがかかってしまいます。
一時的にまぶたが開いて楽に感じることがあっても、長期間の使用や乱暴な取扱いは、筋肉や皮膚のゆるみにつながるため、使用頻度や扱い方には十分注意が必要です。
目を強く擦る
目を擦る癖がある人は、無意識のうちにまぶたに大きな負担をかけている可能性があります。
眼瞼挙筋筋膜は非常に繊細で、強い摩擦や刺激によりダメージを受けやすく、眼瞼下垂の原因になります。花粉症やアトピー性皮膚炎などで目が痒くなる人は、症状を薬でしっかりコントロールし、できるだけ触らないことが重要です。
また、クレンジングや洗顔時にごしごしこすってしまうのも避けましょう。メイク落としは摩擦の少ないアイテムを選び、肌にやさしく触れるようにすることが重要です。
スマホやPCでの長時間作業
スマートフォンやパソコンなどの液晶画面を長時間見続けていると、まばたきの回数が減り、目の周辺の筋肉が緊張状態のまま固まってしまいます。
このような眼精疲労の蓄積は、まぶたの筋肉を弱らせたり、たるみを加速させたりする原因になります。
目元の疲労が続くと、若い方でもまぶたが開きにくくなったり、下がって見えるようになったりするため、意識的に休憩をとることが大切です。1時間に1回は画面から目を離し、遠くを見る習慣をつけると、眼精疲労の予防に効果的です。
まとめ
眼瞼下垂は、加齢や生活習慣などさまざまな要因で、誰にでも起こり得る目元のトラブルです。すべてをトレーニングで改善するのは難しいものの、予防という観点では日々の意識やケアが重要になります。
年齢のせいだから仕方ないと諦めず、自分の目の状態を正しく知るためにも、適切な医療機関での受診も合わせておすすめします。
『ひふみるクリニック』では、眼瞼下垂の手術を数多く行ってきた形成外科専門医が診察を行います。患者さんの心配事や悩みなどにも寄り添う診察を心がけていますので、目元の違和感を感じた際には、ぜひご相談ください。